※本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれている場合があります。

「事実は小説より奇なり」とはいったもので、世の中には架空の話よりも驚くべき実話が往々にして存在する。例えば私、P.K.サンジュンの友人のお父さんは「元プロボクサーで現在は布団屋」なのだが、そんな設定は誰一人として考えつかないハズだ。
今回ご紹介するエピソードもまた「誰も想像できない実話」である。話の主人公は私の母方の祖父──。祖父が7歳の頃、韓国から日本に渡ってきた話だ。
・滅茶苦茶だった祖父
あなたは自分のおじいさん、おばあさんがお好きだろうか? 率直に申し上げて私は母方の祖父が好きではなかった。というのも、正月や盆に母の実家に出かけても祖父がいた試しがほとんどなく、好き嫌いの以前にどんな人間なのか少しもわからなかったためだ。

後に知ったことだが、この時期の祖父は複数の愛人を囲っており、なんなら母を含めた6人兄弟のうち2人は腹違いの子供であった。冷静に見て「金にがめつく女グセが超絶悪い老人」それが私の祖父に対する印象だ。
そんな祖父とそれなりに距離が縮まったのは、私が20歳を越えてから、祖父が亡くなる5年ほど前だっただろうか。母から頼まれ、1人での生活が困難になった祖父に届け物をするのがきっかけだったと思う。
その時すでに祖母は亡くなっており、親戚からは「いかに祖父が滅茶苦茶な人間か」を吹き込まれていたが私も大人になっていたのだろう、好き嫌いの感情とは別に「個性的なじいさんだな」と思うようになっていた。

死の直前に入院していた病院ではひたすら看護婦の手を放さず握りしめ、その昔「息子が住んでいた家を勝手に売り払った」という破天荒な祖父。だが私に直接的な害はなく、祖父なりに孫への愛情もあったのか定期的に会うようになっていた。
・100回以上聞かされた自慢話
祖父の自慢話はいつも13歳の頃から始まる。いわく「13歳の頃に東大卒の初任給の3倍も稼いでいた」というのだ。現在の価値にすると80万円ほどの大金を「わずか13歳で稼いでいた俺……すごいだろ?」というのがお決まりパターンであった。
この13歳の頃は仲間たちと「上京した大学生向けの寮」を営んでいたようで、魚屋から売り物にならないアラをもらって来たり、パン工場から耳をもらったりした……なんて話は死ぬほど聞かされた。この話をきっかけに「いかに自分が商売で成功したのか?」自慢話が延々と始まる。

・祖父が7歳の頃の話
さて、話をメインに戻そう。ズバリ「祖父が7歳の頃に韓国から日本へ渡ってきた理由」である。当時、祖父は釜山からほど近い慶尚南道固城郡というところに住んでいたらしい。当然のように家は貧しく、まだ少年だった祖父も朝から晩まで農作業の手伝いをしていたという。
祖父は1912年生まれだから7歳だと1919年。第一次世界大戦は終結したものの、世界は帝国主義の名のもと国盗り合戦が公然と繰り広げられていた時代である。日本の支配下にあったとはいえ韓国の片田舎の少年の暮らしは、それはそれは貧しかったに違いない。
そんなある日のこと──。祖父の家に日本からお客さんが来たという。どういった目的での来訪かを知る術はないが、7歳だった祖父は色めき立った。なぜなら当時の祖父は「日本に行けば学校に通える」と噂話で聞いていたからだ。

物心ついてから労働に従事する毎日。祖父は「学校」が何であるかをよく知らずとも「学校」という未知なる存在に強烈な憧れを抱いていたのだろう。そしてお客さんが1週間ほどの滞在を終え日本に帰るその日……祖父はとんでもない行動に出た。
なんと祖父はそのお客さんの後をひたすら尾け始めたのだ──。いわゆる “尾行” である。刑事ドラマなどで尾行のシーンはたびたび目にするが、7歳の少年が国をまたいでの尾行なんて聞いたことがあるだろうか? まさに「事実は小説より奇なり」としか言いようがない。
当時は下関と釜山をつなぐ船が日本と韓国を結ぶ交通手段だったというが「子供のことなんか誰も気にしていなかった」らしく、祖父はまんまと日本に上陸した。そして下関で下船後、そのお客さんに「ついて来ちゃった。お腹が空いた」と声をかけたという。

・学校に行きたくて後を尾けた
そのお客さんこそビックリしただろう。7歳の子供が勝手に日本まで着いてきているのだから。その後、お客さんがどんな対処をしてくれたのか、祖父が1度韓国へ戻ったのか、それともそのまま日本に居ついたのかはわからない。確かなのは「13歳の頃には東大生の3倍の給料をもらっていた」という事実だけである。
ここからは私の推測だが、おそらく祖父はストリートチルドレンまがいな生活をしながら東へ東へ流れ、後に母の実家となる東京都北区周辺に辿りついたのだと思う。
心優しい日本人に助けられたのか、それとも韓国コミュニティの隅っこで生きながらえたのかは、今となっては闇の中だ。ただ祖父が決して語ることがなかった「7歳から13歳までの空白の6年間」は、想像を絶する貧しさと苦しみがあったに違いない。

そう思えるようになってから、祖父のことが好きになることは無いにせよ嫌いになることもなかった。ただ単に「私が祖父のところへ行くと母が喜ぶから」という理由が一番であったが、祖父が94歳で亡くなる間際まで私は定期的に祖父のもとへ足を運んだ。
祖父は「子供だから山を越えれば日本だと思っていた」とも話していたが、この無知とも無謀ともいえる7歳の少年の行動が、少なからず私がこの世に生を受ける起因になっているのならばやはり感謝すべきなのだろう。貧しき7歳の正夫少年よ、どうもありがとう──。
執筆:P.K.サンジュン
Photo:RocketNews24.
Source: ロケットニュース24
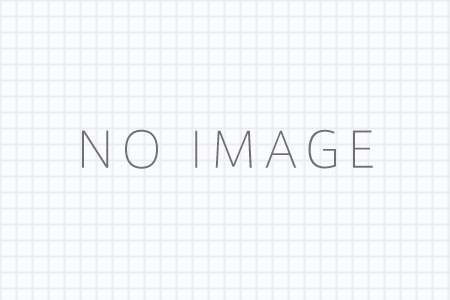







コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。